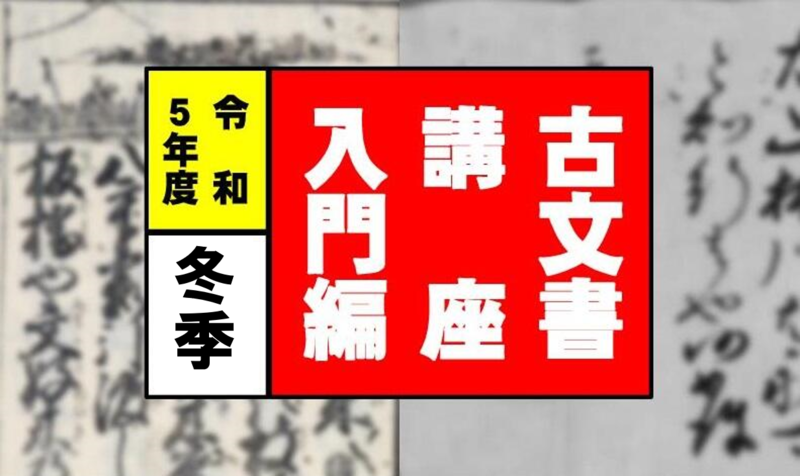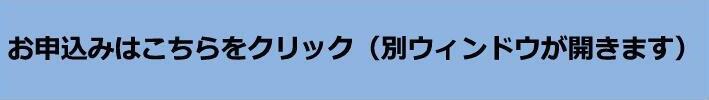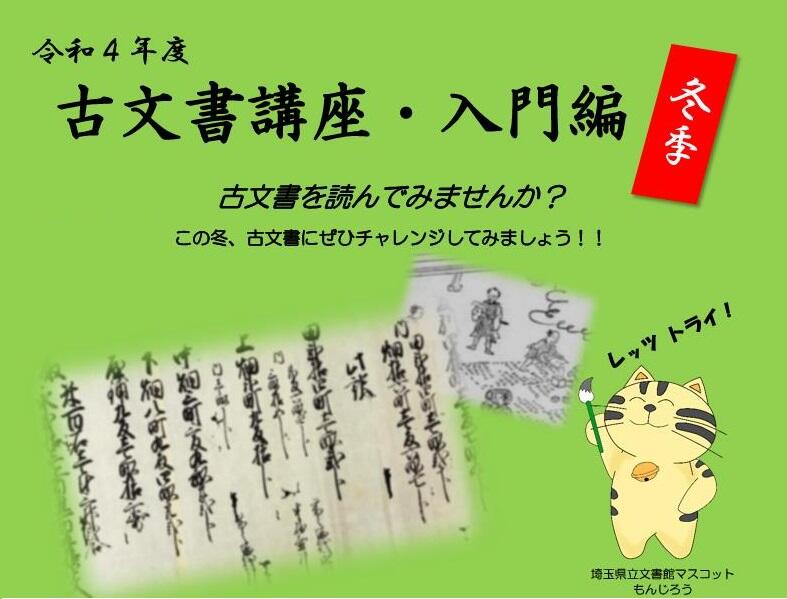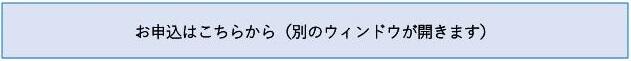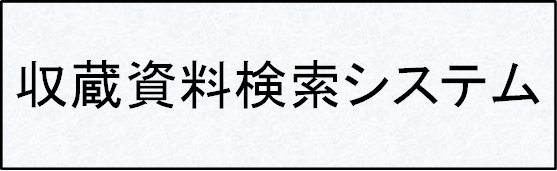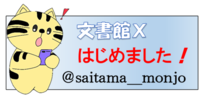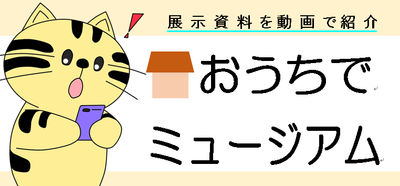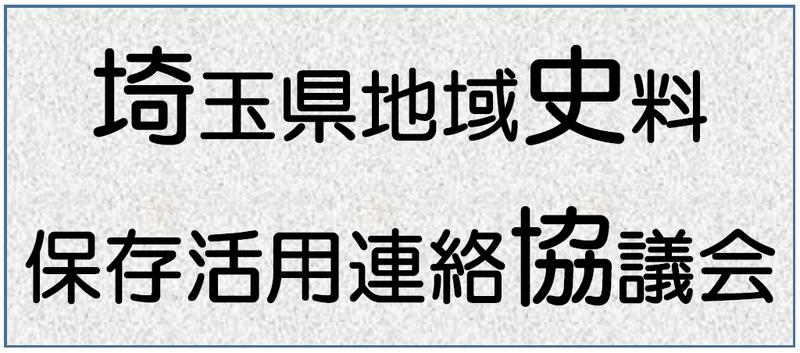令和5年度 古文書講座・入門編(冬季)
古文書を読んでみませんか?
当講座は、古文書を読み始める方向けの入門講座です。
「歴史に関心はあるけどくずし字が読めない」「文章の意味がわからない」「自分の目で史料を読んでみたい」といったお悩みに一緒に挑戦してみませんか?
当館収蔵のここでしか読めない資料をテキストに、埼玉の歴史と古文書の世界に分け入ってみましょう。
※春季講座と同一内容です。
日 時 【第1回】令和6年1月11日(木曜日) 10時00分~11時30分
【第2回】 18日(木曜日) 10時00分~11時30分
【第3回】 25日(木曜日) 10時00分~11時30分
全3回の講座です。
※受付は9時30分からとなります。
※各回10~15分程度の休憩をとります。
対 象 ・県内在住・在勤・在学で、古文書に初めて接する方や古文書の勉強を始めたばかりの方
・全3回参加できる方
会 場 文書館講座室(3階)
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-18(JR浦和駅西口から徒歩15分)
※駐車台数が限られているため、来場には公共交通機関を御利用ください。
定 員 80名(申込多数の場合は抽選で決定します)
参加費 500円(テキスト代)
申込期間 令和5年12月1日(金)9時00分から 12月20日(水)23時59分まで
※申込期間終了しました
申込方法 ①埼玉県電子申請・届出サービス
https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=47509&accessFrom=
下記のバナーからも申込サイトに入れます。
必要事項を入力してお申込みください。折り返し「申込完了通知」が自動送付されます。
システムの使い方については、サイト内のヘルプを御確認ください。
※1人につき1口の申込みが必要です。
※内容についてご不明な点は、担当まで御連絡ください。
※操作についてのお問い合わせは電子申請コールセンターまでお願いします。
固定電話コールセンター
TEL :0120-464-119
(平日 9:00~17:00 年末年始除く)
携帯電話コールセンター
TEL :0570-041-001(有料)90円/3分
(平日 9:00~17:00 年末年始除く)
FAX :06-6455-3268
電子メール: help-shinsei-saitama@s-kantan.com
②往復はがき
往復はがきに郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・電話番号を明記してお申し込みください。
・宛先 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-3-18 埼玉県立文書館 古文書担当
・12月20日消印有効
受講通知 受講の可否については、申込締切後1週間を目途にメールでお知らせします。
申込が定員を超えた場合は抽選となりますので、あらかじめ御了承ください。
連絡先 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-3-18 埼玉県立文書館 古文書担当
(電話番号)048-865-0112
講座は終了しました
古文書を読んでみませんか?
当講座は、「関心はあるけれどくずし字が読めない」「文章が難しくて意味がわからない」「自分の目で史料を読んでみたい」といった、古文書を読み始める方向けの入門講座です。
当館収蔵のここでしか読めない資料を用いて、当館学芸員とともに古文書を読み込み、埼玉県の歴史の世界に分け入ってみましょう。(春季と同じ講義内容です)
日 時 【第1回】令和5年1月12日(木曜日) 10時00分~11時30分
「古文書を読んでみよう」
【第2回】令和5年1月19日(木曜日) 10時00分~11時30分
「江戸時代の年貢に関する文書を読む」
【第3回】令和5年1月26日(木曜日) 10時00分~11時30分
「江戸時代の往来物を読む」「古文書を読むコツ」
全3回の講座です。
※令和4年度「古文書講座・入門編」(春季)と同じ内容です
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、開催方法が変更になる場合があります。
※受付は9時30分からとなります。
※各回10~15分程度の休憩をとります。
対 象 ・県内在住・在勤・在学で、古文書に初めて接する方や古文書の勉強を始めたばかりの方
(高校生以上)
・全3回参加できる方
会 場 県立文書館 3階 講座室
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-18(JR浦和駅西口から徒歩15分)
※駐車台数が限られているため、来場には公共交通機関を御利用ください。
定 員 30名(申込多数の場合は抽選で決定します)
参加費 500円(テキスト代)
申込みは締め切りました。たくさんのお申し込みありがとうございました。
申込期間 令和4年12月1日(木)9時00分から15日(木)17時00分まで
申込方法 埼玉県電子申請・届出サービス
必要事項を入力してお申込みください。折り返し「申込完了通知」が自動送付されます。
システムの使い方については、サイト内のヘルプを御確認ください。
メールが届かない場合は当館へお問合わせください。
下記のボタンから申込サイトに入れます。
※電話、FAX、メール、来館による申込はお受けできませんのでご注意ください。
※1人につき1口の申込みが必要です。
※不明な点は、担当まで御連絡ください。
受講通知 受講の可否については、申込締切後1週間を目途にメールでお知らせします。
申込が定員を超えた場合は抽選となりますので、あらかじめ御了承ください。
連絡先 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-3-18 埼玉県立文書館 古文書担当
(電話番号)048-865-0112
【開館時間】
午前9時~午後5時
【休館日】
・月曜日(県民の日に当たるときは、その翌日)
・毎月末日(令和7年5.8.11月.令和8年1.2月の末日は開館)
・祝日
・年末年始(12月29日~翌1月3日)
・特別整理期間(令和7年5月14日~23日、10月22日~31日)