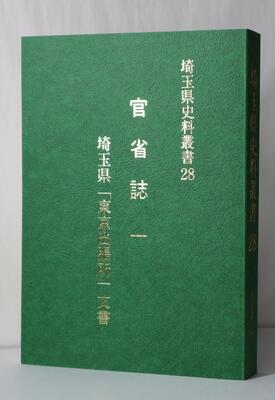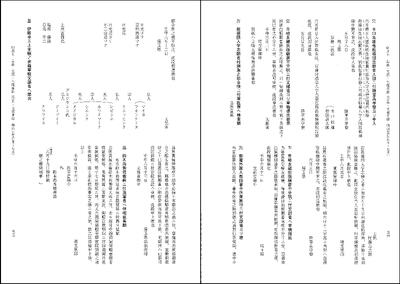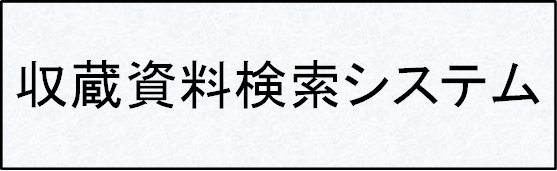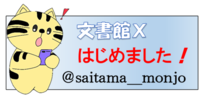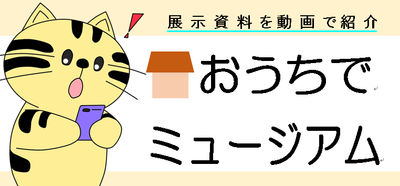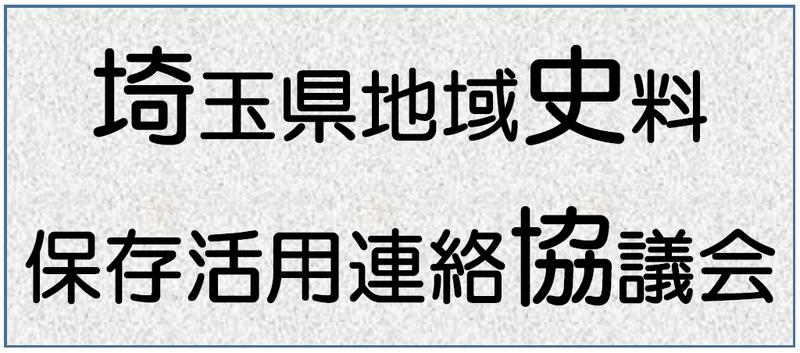● 『埼玉県史料叢書』第28巻「官省誌一 埼玉県「東京出張所」文書」を刊行しました!●
『埼玉県史料叢書』(さいたまけんしりょうそうしょ)は、埼玉県の歴史と文化を知る素材となる重要な史料を翻刻・編集した史料集です。
この度、第28巻として『官省誌一 埼玉県「東京出張所」文書』を刊行する運びとなりました。書名の「官省誌」とは、「埼玉県行政文書」(国指定重要文化財)の内、明治初年に東京・常盤橋門内(現東京都千代田区)の旧越前藩邸に設けられた埼玉県東京出張所が、政府の各官庁とやり取りした文書等の記録です。本書には明治5年(1872)から翌6年(1873)までの史料の一部を収録しました。
江戸幕府から明治新政府へ、そして地方制度が藩から府県へと大きく変わる中で、政府や埼玉県が江戸時代の遺産を受け継ぎつつ、明治という新たな時代を切り拓いた様子を伝える史料を、ぜひ御一読ください。
書影
●主な収録史料●
1 村の移管に関わる大蔵省とのやり取り(本書92ページ)
(史料名「多摩郡南小曽木村他三ヶ村願ノ儀元岩槻県ヨリ大蔵省ヘ伺」)
明治5年(1872)、埼玉県の前身である旧岩槻県から大蔵省へ宛てた伺書です。多摩郡南小曽木村(現東京都青梅市)などの村々を神奈川県に引き渡す際、村々から神奈川県が遠いため難しいという願い出があったため、どうすればよいかを大蔵省へ問い合わせています。
大蔵省からは、村々の願い出は不採用としてなお一層説諭すべしとの回答がありました。
2 学校の設置に関わる文部省とのやり取り(本書57ページ)
(史料名「学校取設ノ儀ニ付文部省ヘ願」)
明治5年(1872)に埼玉県から文部省へ宛てた願書です。埼玉県内で忍・浦和・岩槻の旧県から学校を引き継いだものの、教育が行き届いていないため、学校を更に設置する許可を求めています。対する文部省からは、これを許可するとともに、学制が出された場合はそれに沿うべしとの回答がありました。
学校の制度が整備される以前から、埼玉県独自で学校設置を模索し、政府とのやり取りを行っていたことが分かる史料です。
本文見本
●有償頒布●
『埼玉県史料叢書』は埼玉県県政情報センターにて有償頒布しています。
購入希望の方は、同センターまでお問い合わせください。
住 所:さいたま市浦和区高砂3-15-1(県庁 衛生会館1階)
電 話:048-830-2543
本巻頒布価格:2,855円(税込)
●令和元年度刊行『埼玉県史料叢書』第21巻「埼玉新聞社撮影戦後報道写真 フィルムのなかの埼玉1947-1964」の情報はこちらをご覧ください。
●第1巻・第2巻・第13巻(上)・第13巻(下)はご好評いただき、完売いたしました。文書館・図書館などでご利用ください。
|
巻数 (発行年月日)
|
内容
|
|
「埼玉県史料 一」 (1994年3月刊) |
明治政府は、明治7年11月、太政官布告を出して、明治維新以来の歴史をまとめるため、『府県史』の編集(明治4年の県庁創始期~明治7年12月及び維新以降の旧藩と旧県の史料をまとめる)を命じました。それをうけて埼玉県でまとめられたのが「埼玉県史料」です。明治8年以降についても、各県で継続編さんすることが求められたため、「埼玉県史料」は、全体では、明治元年~明治17年の史料が収録されています。これを翻刻したのが、この埼玉県史料叢書の第1~5巻です。 第1巻では、政治部が扱っていた<県治、勧農・勧業、工業、刑罰、賞典・褒賞>を収録しました。 |
|
第2巻【完売】 「埼玉県史料 二」 (1995年3月刊) |
「埼玉県史料」を翻刻した分冊の第2冊めです。内容は、政治部が扱っていた<賑恤、祭典、戸籍・戸口、民俗、学校、駅逓、警保、忠孝節義、災異・騒擾時変、衛生、議会>を収録しました。 |
|
第3巻 「埼玉県史料 三」 (1997年3月刊) |
「埼玉県史料」を翻刻した分冊の第3冊めです。内容は、制度部が扱っていた<租法、職制>を収録しました。租法では、租税徴収のための法制、職制では、県・郡・区町村における分課組織とその所掌事務等の変遷を扱っています。 |
|
第4巻 「埼玉県史料 四」 (1998年3月刊) |
「埼玉県史料」を翻刻した分冊の第4冊めです。第3巻に引き続いて、制度部の<兵制、禁制>などの他、<官員履歴>や地誌的な分野として<社寺之部><古址遺跡碑文等之部>などが収録され、明治初年の県内各地の風景や神社、城館跡などの挿絵・図版が豊富に織り込まれています。また、明治10年の地理の教科書「埼玉県地誌略」も収めました。 |
|
第5巻 「埼玉県史料 五」 (2001年3月刊) |
「埼玉県史料」を翻刻した分冊の第5冊めです。埼玉県は明治4年に誕生しますが、それに先んじて岩槻、大宮・浦和、忍の旧藩・旧県が存在しました。第5巻はこれら旧藩・旧県の史料を収録しました。明治4年7月の廃藩置県前後の県政の動向を知ることができる基本史料です。さらに別冊として1~5巻の索引(地名・人名・事項・法令)を添付しました。 |
|
「入間・熊谷県史料 一」 |
明治元年から同6年6月までの、現県域の荒川以西の地域にあたる旧藩県及び入間県に関する史料をまとめました。上巻は、川越藩(県)布達と上申・指令・往復文書、入間県の上申・指令・往復文書と布告を収録しました。激動の明治維新期の地域の状況を知ることができる基本史料です。 |
|
第6巻(下) 「入間・熊谷県史料 二」 (2009年3月刊) |
明治4年11月から同6年6月までの、現県域の荒川以西の地域にあたる入間県に関する史料をまとめました。上巻に引き続き、下巻では入間県布告・布達集、入間県職員録、入間県等職員履歴、入間県戸長名簿を収録しました。近代黎明期におけるこの地域の状況を知ることができる基本史料です。 |
|
「入間・熊谷県史料 三」 |
明治6年6月から明治9年8月にかけて、現在の埼玉県西部と群馬県をあわせた地域に成立していた熊谷県に関する史料集です。上巻には、熊谷県時代に県下へ発せられた布達を編年順にまとめて収録しました。県政の動向を知ることができる基本史料です。 |
|
「入間・熊谷県史料 四」 |
明治6年6月から明治9年8月にかけて、現在の埼玉県西部と群馬県をあわせた地域に成立していた熊谷県に関する史料集です。下巻には、「上申・指令・往復文書」「考績録」「学務年報」「演説書」「引継書類目録」を収録しました。熊谷県の行政課題を知ることができる基本史料です。 |
|
第8巻 「明治期産業土木史料」 (1996年3月刊) |
埼玉県立文書館で保存・公開している埼玉県行政文書のなかから、明治期の産業とその流通面での基盤となった道路・河川に関するまとまった史料3点[埼玉県誌資料、公益道路調、河川調]を収録しました。明治期埼玉の産業・道路・河川の全容を通観する史料集です。 |
|
第9巻 「明治大正期知事事務引継書 一」 (1999年3月刊) |
明治30年から大正3年の間に行われた知事交替時の事務引継書を収録しました。この時期の知事は官選の地方官であり、政府の任免によって頻繁に交替しています。その際の引継書には様々な資料が添付され、各時期の埼玉県政の現況を知る格好の史料です。 |
|
「明治大正期知事事務引継書 二」 (2004年3月刊) |
第9巻の続巻で、大正5年から大正8年の間に行われた知事交替時の事務引継書を収録しました。知事の事務引継書は、その時期の県の重要政策をダイジェスト的にまとめており、当時の埼玉県政の現況を知る格好の史料です。 |
|
(2005年3月刊) |
第9巻・第10巻(上)の続刊として、大正12年の堀内知事から元田知事への引継ぎと、大正13年の元田知事から斎藤知事への引継ぎを収録しました。 |
|
第11巻 「古代・中世新出重要史料 一」 (2011年3月刊) |
「古代新出重要史料」では、古代の木簡や刻書・刻画紡錘車、墨書土器・刻書土器、文字瓦等、出土文字資料のうち、埼玉と関わりのある資料を、写真・図表と共に解説を交え収録しました。 「中世新出重要史料」では、『新編埼玉県史』刊行後に新たに確認された史料を中心に、鎌倉~室町時代の埼玉県に関する中世文書を編年順に収録しました。 |
|
第12巻 「中世新出重要史料 二」 (2014年3月刊) |
前巻に収録された鎌倉時代から室町時代までに続き、戦国時代の新出重要史料を収録しています。戦国時代の本県は、古河公方・両上杉氏・後北条氏といった戦国大名がしのぎを削る場所でした。そうした中で、忍成田氏や羽生木戸氏、岩村太田氏といった中小規模の武将たちは生き残りを懸けて、様々な活動をしていました。本巻ではこうした激動の時代の文書1,282点を収録しています。また、天正18年(1590)以降の文書の一部を収録しているので、今までわからなかった後北条氏滅亡後の動向を知ることもできます。本県のみならず、関東の戦国時代について知るためには、必読の一書です。 |
|
第13巻(上)【完売】 「栗橋関所史料 一 御関所御用諸記1」 (2002年3月刊) |
五街道のひとつである日光道中、その途次利根川の渡河点にある栗橋関所の関所番を務めた足立家に伝わる県指定文化財「栗橋関所日記および関係資料」から、栗橋関所の関所番を務めた足立金四郎が、元禄10年(1697)から天保15年(1844)までの関所日記から記事を書き抜いたと思われる史料を、編年順に集成したものの上巻です。当時の関所や交通政策の実態をうかがい知ることができる格好の史料です。 |
|
第13巻(下)【完売】 「栗橋関所史料 二 御関所御用諸記2」 (2003年3月刊) |
埼玉県立文書館に収蔵されている足立家文書のなかから、栗橋関所の関所番を勤めた足立金四郎が、元禄10年(1697)から天保15年(1844)までの関所日記から記事を書き抜いたと思われる史料を、編年順に集成したものの下巻です。当時の関所や交通政策の実態をうかがい知ることができる格好の史料です。 |
|
第14巻 「栗橋関所史料 三 御関所日記書抜Ⅰ」 (2010年3月刊) |
埼玉県立文書館に寄託されている足立家文書のなかから、栗橋関所の関所番を勤めた足立正寛が天保12年(1841)から慶応2年(1866)までの御関所御用諸記から記事を書き抜いたと思われる史料「御関所日記書抜」のうち寛政元年(1789)から文久元年(1861)までを収録しました。幕末に来日した外国人の関所通行記録や大名の国替えにともなう武器弾薬の移送など、当時の緊迫した情勢を関所番の目を通してうかがい知ることができる好史料です。 |
|
第15巻 「栗橋関所史料 四 御関所日記書抜 Ⅱ 御用留 Ⅰ」 (2012年3月刊) |
前巻に引き続き、足立家十代目の足立正寛が編纂した「御関所日記書抜」のうち、文久元年 (1861)5月~同3年12月までの残り3冊分を収録。同じく「御用留」全15冊のうち、文久3年12月~慶応元年(1865)6月までの10冊分を収録しました。幕末期水戸藩の尊王攘夷派による天狗党の乱に関係した記事が多く、追討する幕府軍の関所通行やそれに伴う武器・弾薬の運搬の様相、危機的状況のなか情報収集に奔走する番士の奮闘がうかがえる貴重な史料です。 |
|
第16巻 「栗橋関所史料 五 御用留 Ⅱ 御関所日記 」 (2013年3月刊) |
前巻に引き続き、足立家十代目の足立正寛が編纂した「御用留」全15冊のうち、慶応元年(1865)12月~明治2年(1869)3月までの残り5冊分を収録し、原本である「御関所日記」全6冊を収録しました。さらに、「御関所御用諸記」(埼玉県史料叢書第13巻(上)(栗橋関所史料一)に掲載されていなかった「安永期の社参」が書かれている「御社参御用留」を収録しました。 戊辰戦争が勃発し、江戸幕府から明治新政府へ移行するまさに激動の時代。各地で繰り広げられる生々しい争乱の状況や、それにともなう番士の情報収集、そして関所勤番や番士自身の身分をめぐる奮闘ぶりなど、「栗橋関所の終焉」がうかがえる貴重な史料です。 なお、「御関所御用諸記」(第13巻(上))に掲載されていなかった「安永期の社参」が書かれている「御社参御用留」を収録しました。 |
|
第17巻 「埼玉県布達集 一 明治八年七月~十一年十二月」 (2015年3月刊) |
「埼玉県布達集」は、明治8年7月から埼玉県報が発行される明治19年8月までの11年間に、埼玉県が広く県民に向かって出した布達や諭達を網羅的に収録し、全4巻にまとめるもので、その第1巻目となります。「埼玉県布達集一」には、明治8年7月から同11年12月までの布達類538点を収録しています。 埼玉県立文書館で収蔵する重要文化財「埼玉県行政文書」や古文書の中から、県政の基本史料となる明治初期の重要な布達を集めて初めて刊行するものです。埼玉県内の様々な分野の状況や行政の対応を具体的に知ることができる、埼玉県政の基本史料といえます。 |
|
第18巻 「埼玉県布達集 二 明治十二年一月~十四年十二月」 (2016年2月刊) |
前巻に引き続き、「埼玉県布達集」は、明治8年7月から埼玉県報が発行される明治19年8月までの11年間に、埼玉県が広く県民に対して出した布達や諭達を網羅的に収録したものです。全4巻で、本巻はその第2巻目となります。「埼玉県布達集二」には、明治12年1月から同14年12月までの布達類509点(管内一般に布達した甲号以外の重要なもの)を収録しました。 |
|
第19巻 「埼玉県布達集 三 明治十五年一月~十六年十二月」 (2017年2月刊) |
「埼玉県布達集」の第3巻目となる本巻には、明治15年1月から明治16年12月までの布達類448点を収録しました。 いわゆる「松方財政」によって地方経済・県民生活が苦境に陥る一方、自由民権運動の高揚が見られる中、本県が災害被災者の救済、就学率の向上、伝染病の対策や勧業政策などの様々な施策に取り組んだ様子を如実に示す史料集です。 |
|
第20巻 「埼玉県布達集 四 明治十七年一月~十九年八月」 (2018年2月刊) |
「埼玉県布達集」の最終巻の本巻には、明治17年1月から、「県報」の刊行により布達の発行が終了する明治19年8月までの布達類414点を収録しました。憲法制定に向けた諸制度の整備への対応、蚕糸業・茶業など重要産業の振興、経済不況への対策、秩父事件への対応など、同時期の本県の取り組み、そして県民生活の一端を明らかにする文書を収録した史料集です。 |
|
第21巻 「埼玉新聞社撮影戦後報道写真 フィルムのなかの埼玉1947-1964」 (2020年2月刊) |
埼玉新聞社が撮影し、のちに県立文書館に寄贈された50万コマ以上のフィルムの中から、終戦後間もない昭和22年(1947)から東京オリンピックが開催された昭和39年(1964)までに撮影された512点の写真を厳選して掲載しました。 |
|
第22巻 「小室家文書一 三代小室元長日記」 (2019年2月刊) |
比企郡番匠村(現ときがわ町)に住み、代々産科の医師として活躍した小室家に伝わった小室家文書のうち、三代目当主の小室元長が文政9年(1826)から嘉永4年(1851)までに記した日記25冊と小室家やその医術についての理解を深められる参考史料8点収録しています。 |
|
第23巻 「小室家文書二 四代小室元貞日記」 (2021年2月刊) |
小室家四代目当主の小室元貞が、天保3年(1832)から同11年(1840)までに記した日記23冊と、安政5年(1858)、元貞最晩年に記した日記1冊の、計24冊分の記録を収録しました。近世後期の医療活動のほか、村人たちの生業、生計、さらには年中行事や通過儀礼に関することなど、多様な内容が記録されています。 |
|
第24巻 「小室家文書三 五代小室元貞日記」 (2022年2月刊) |
小室家五代目当主の小室元長が記した日記と旅行記を収録しました。幕末から明治初期における医療を中心とした社会情勢や、旅行文化、「好古家」の興味関心などをうかがえます。 |
|
第25巻 「栗橋関所史料六 雑事聞書Ⅰ 日光御参詣御用中書留」 (2023年2月刊) |
埼玉県立文書館収蔵の足立家文書から、栗橋関所の関所番を勤めた足立家七代目当主、十右衛門が主に作成した記録「雑事聞書」と徳川家慶の日光参詣準備記録である「日光御参詣御用中書留」など計21冊を収録しました。「雑事聞書」には、十右衛門の身辺での出来事から幕政の風聞まで、様々な情報が記されています。また「御用中書留」には、物品や大名家の通行など社参準備の様相をみることが出来ます。既刊「栗橋関所史料一から五」とは史料の性格が異なり、関所番士として生きた人物の教養や情報に対する姿勢をうかがうことができる好史料です。 |
|
第26巻 「栗橋関所史料七 雑事聞書Ⅱ」 (2024年2月刊) |
「栗橋関所史料」第七巻にあたる本巻には、足立家7代目当主の十右衛門が記した雑事聞書や、10代目足立柔兵衛が、明治2年(1869)に記した記録などを、その他補遺史料と併せて20冊の史料を収録しました。雑事聞書の内容は雑多なものですが、江戸時代後期を生きた人物の心情や思想、社会への関心がうかがえる興味深い史料です。 |
|
第28巻 「官省誌一 埼玉県「東京出張所」文書」 (2025年2月刊) |
「埼玉県行政文書」(国指定重要文化財)の内、明治初年に東京・常盤橋門内(現東京都千代田区)の旧越前藩邸に設けられた埼玉県東京出張所が、政府の各官庁とやり取りした文書等の記録である「官省誌」を収録したシリーズの1冊目です。
本書には明治5年(1872)から翌6年(1873)までの史料の一部を収録しました。 |
【開館時間】
午前9時~午後5時
【休館日】
・月曜日(県民の日に当たるときは、その翌日)
・毎月末日(令和7年5.8.11月.令和8年1.2月の末日は開館)
・祝日
・年末年始(12月29日~翌1月3日)
・特別整理期間(令和7年5月14日~23日、10月22日~31日)
展示案内はこちら